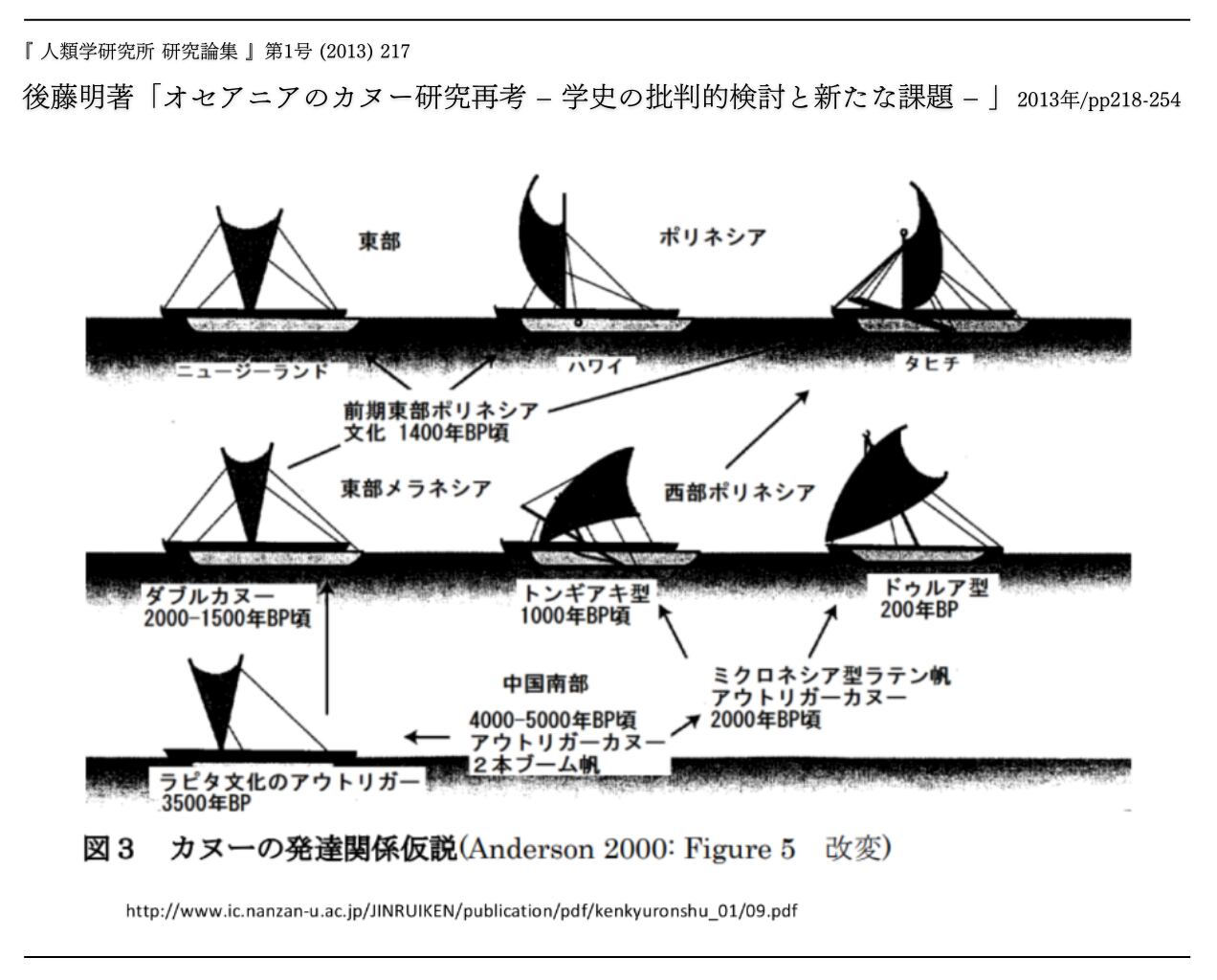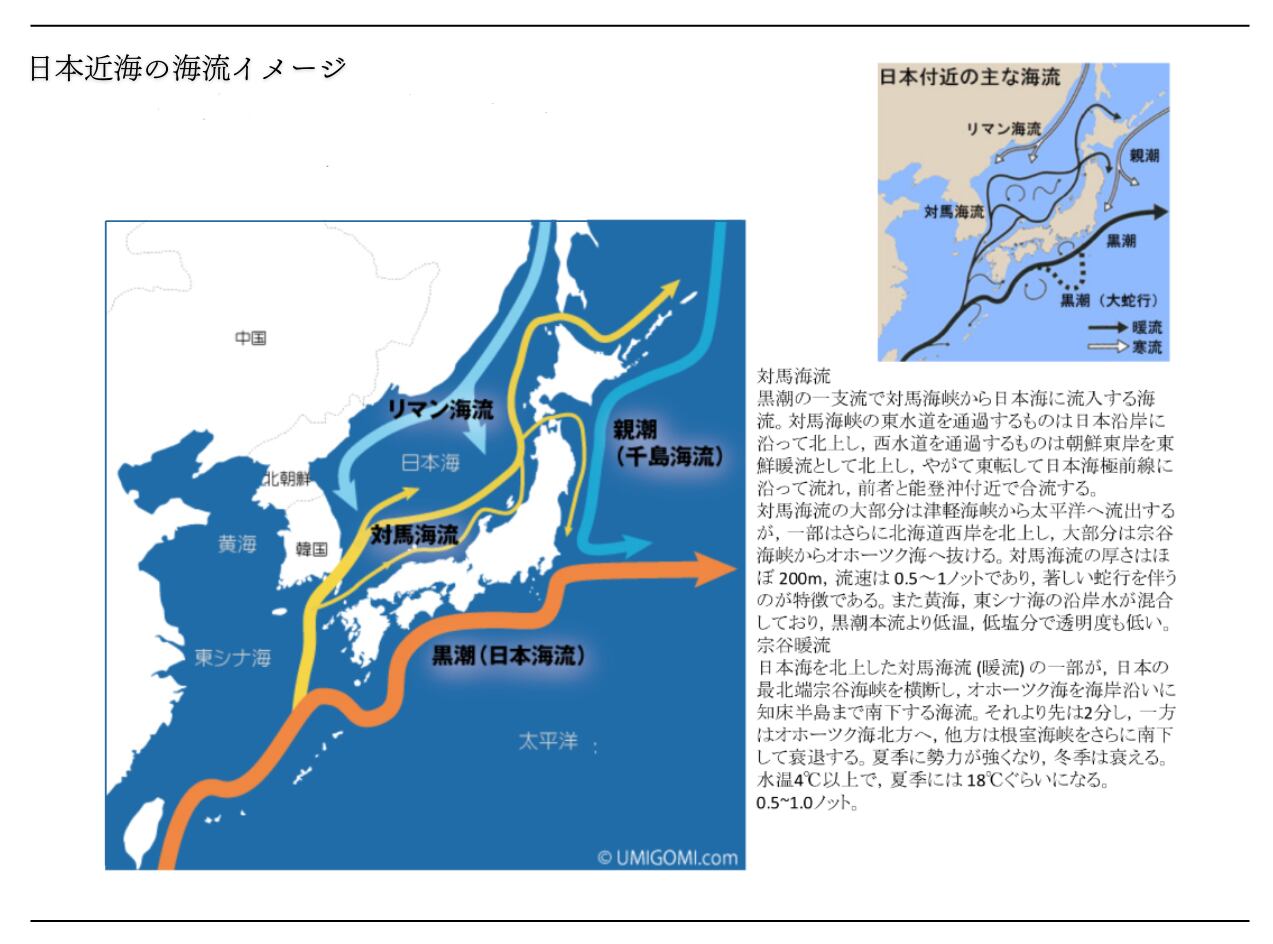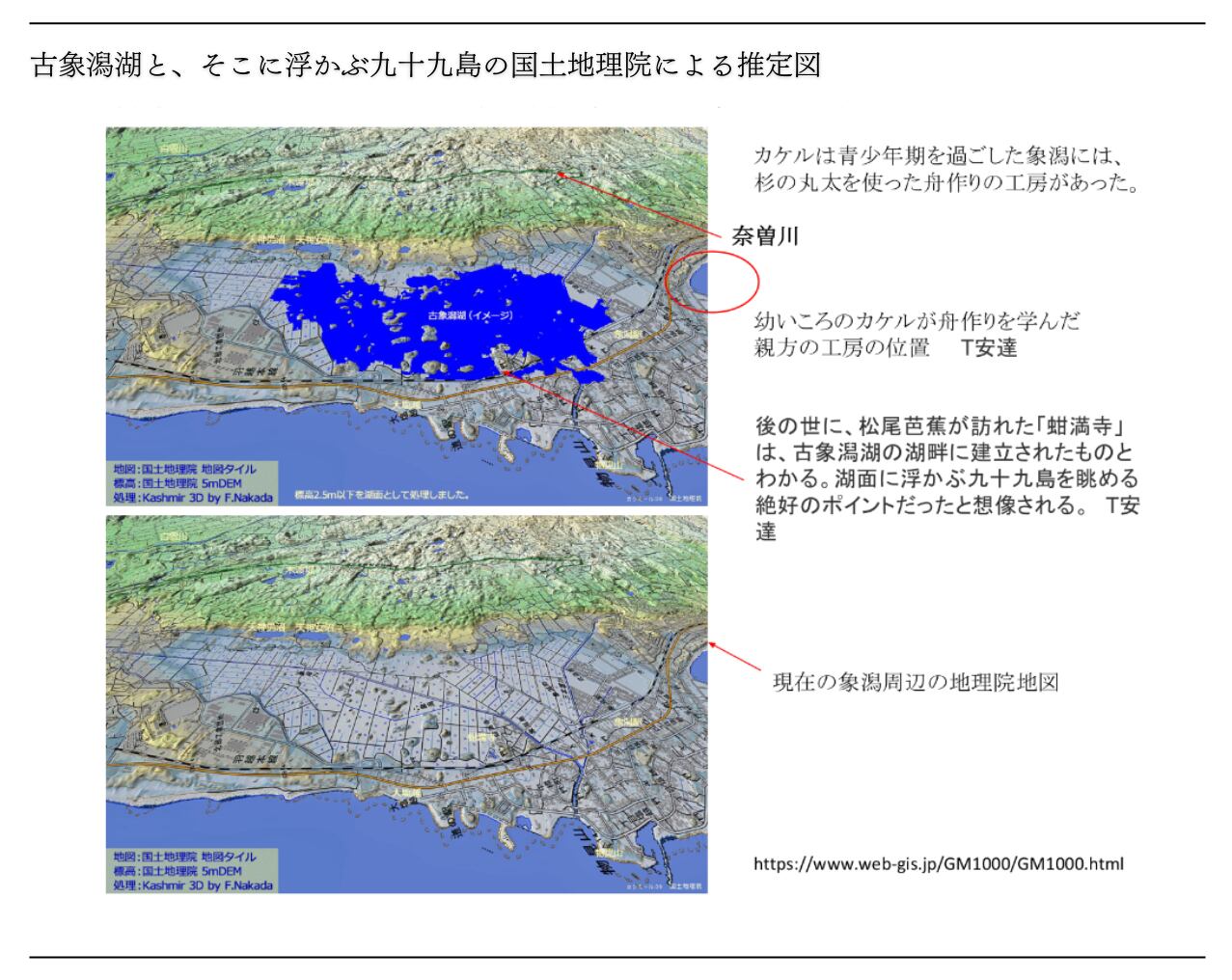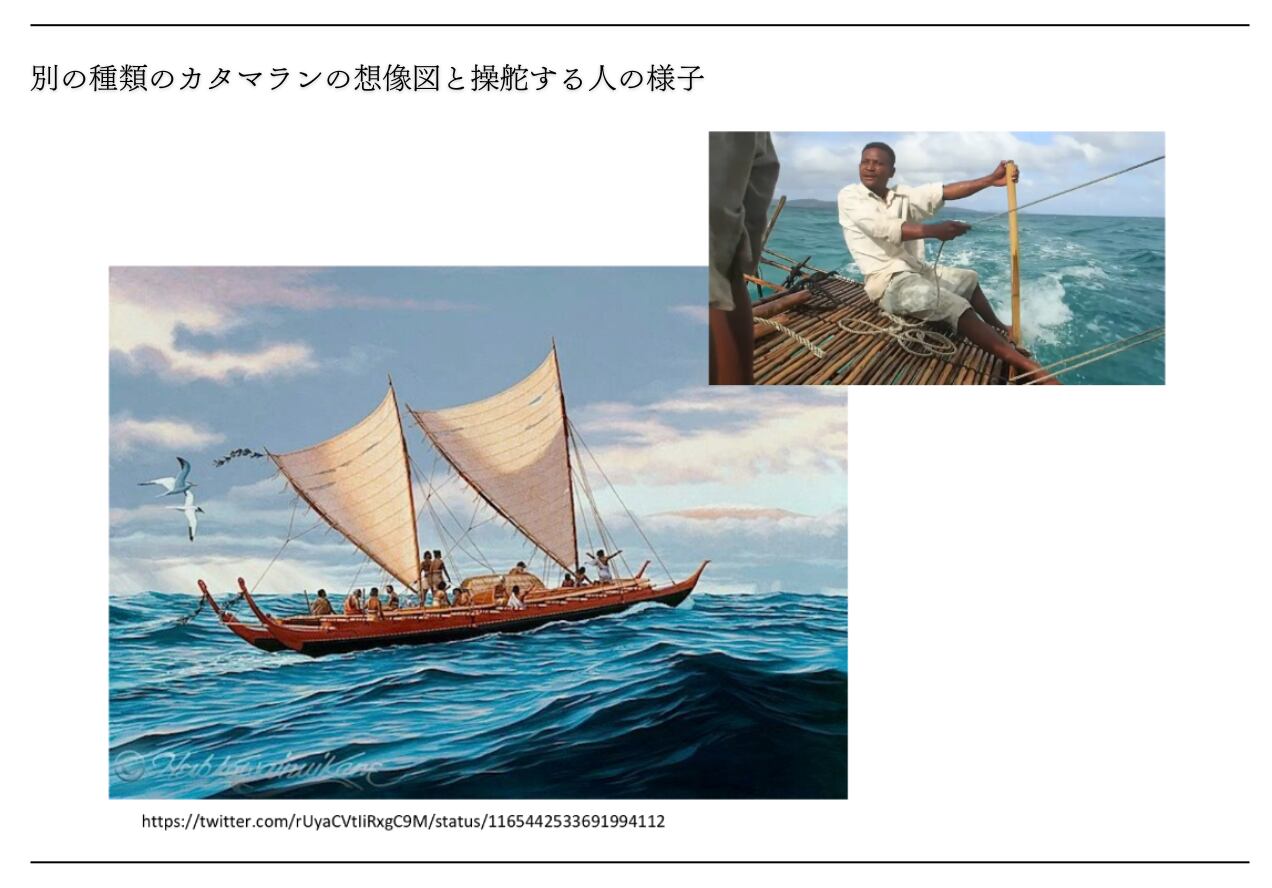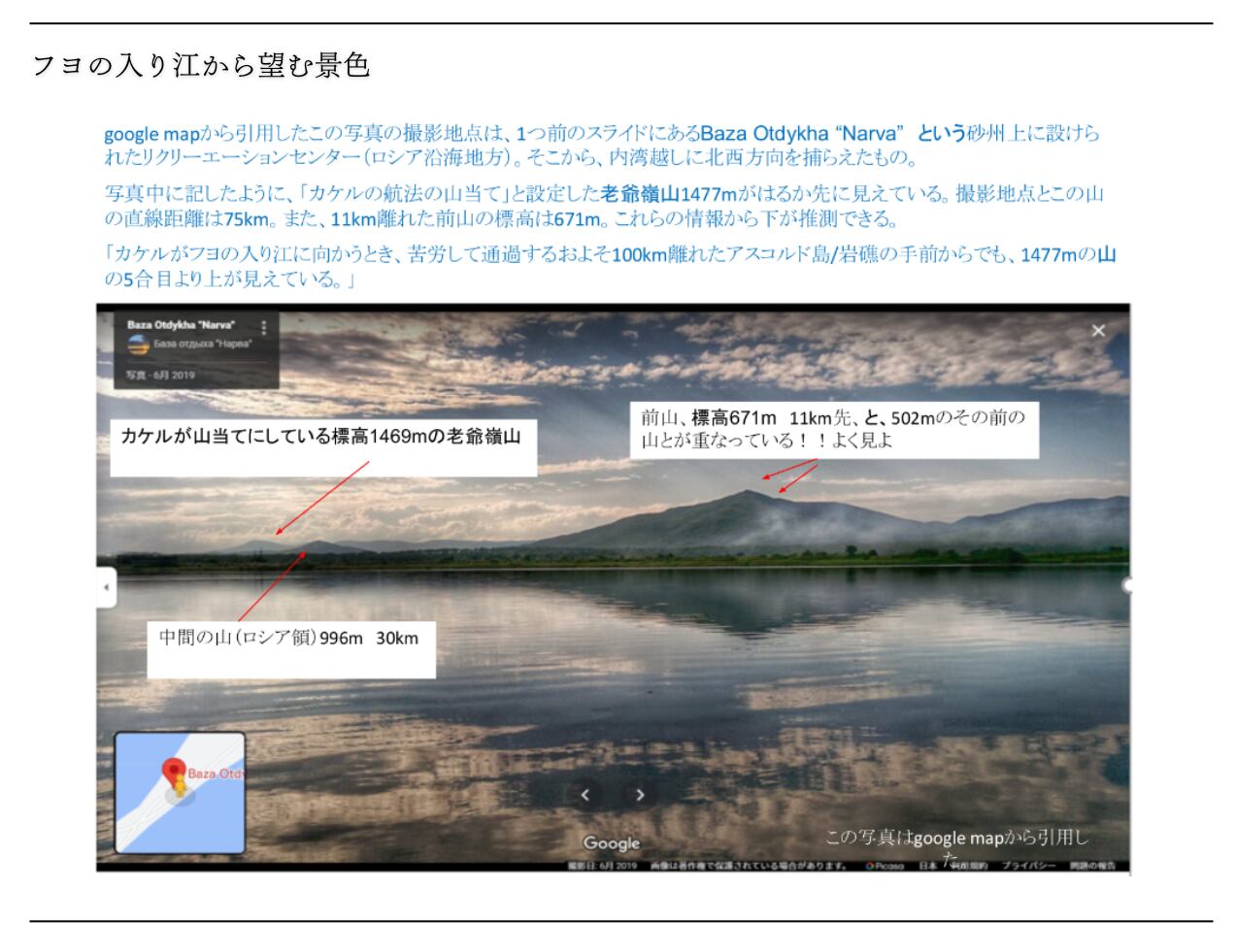ヒダカの舟乗りたち
カケル - 舟長
舟長(ふなおさ)として、北ヒダカ ― 現在の青森 ― の十三湊から日本海を渡り、大陸と交易している。
その日。
カケルは、雲の高さや動き、太陽の陰りや輝きを見る。
風の強弱、波の寄せ具合、鳥や虫の鳴き声で出航を決めた。
ヒダカからは、春から夏にかけて出航する。
冬だと海の上で凍えてしまうからだった。
13名が乗る舟は出航した。
目指すは、大陸の “ フヨの入り江 ” 。
帆で風を受けて進み、潮の流れに乗る。
海の色、太陽と星の位置で方向をたしかめる。
ときには櫂(かい)でこぐ。
舵をとるカケルが「えーんや」と声をかける。
舟子は「おーい」と応じて櫂をこぐ。
航海ルートは北寄り。
海流に乗るためでもあるが、南を通ると賊に襲われやすくなるというのもある。
命がけの舟旅となるが、特別なことではない。
多くのヒダカ人が、大陸と交易していた。
カケルは、ヒダカの象潟(さきかた) ― 現在の秋田県にかほ市― に生まれて育つ。
幼いころから舟づくりを手伝っていた。
舟つくりには、杉の大木を使う。
それを火で炙って、炭にしてから削る。
削った部分に水を貯めて、焼けた丸石を入れて沸騰させて、木を柔らかくしてからさらに削る。
多くの道具は、石でできていた。
鉄の道具であれば、作業の進み具合が断然に異なる。
鉄の需要は高くなっていた。
いい舟を作るために…と、舟に乗ることを覚えたカケルだったが、そっちが主になる。
能代の湊 ― 現在の秋田県能代市 ―まで舟を進める。
さらに高志 ― 現在の北陸 ― まで進んだときには、黒泥 ― 現在のアスファルト ― に目をつけて、他の湊まで運んだ。
これで利益を得たことより、カケルの舟の帆は立派な麻布製となる。
鳥見山 ― 現在の鳥海山 ― は、海の沖合いからでもよく見える高い山。
大昔から、舟乗りたちにとって欠かすことのできない目印だった。
カケルも、海からこの山を見ながら舟を進めた。
そして、10年前。
カケルは仲間と、北の島に舟で向かう。
ヒダカの人々が、「決していこうとするな」と口をそろえた、さらに自然が厳しくなる地だった。
舟は、利尻島までたどり着く。
かすかに、カラフトが見えるところまでいったが、遭難に遭い、仲間を死なせてもいる。
そうした経験から、カケルは独自の航法を編み出している。
タケ兄 - ベテラン舟乗り
タケ兄は、十三湊で出港の準備している。
初めて見る者が、「こんなにも載るのか」と驚くくらい荷物がある。
舟に積見込んだ荷物には、網をかぶせて太縄できつくしめる。
油をひいた麻布で覆い、膠(にかわ)で固める。
周りには竹で編んだ垣を立てて、波が直に当たるのを防ぐ。
積荷は、このところは米俵が多い。
大陸からは鉄の小板を運んでくる。
さまざまな道具の材料が、石や土から鉄へ変わろうとしていた。
稲穂を刈り取るための、鉄の小刀をよく頼まれる。
刈り取った稲穂の脱穀で使う、鉄の櫛も。
多くの鉄の道具も、大陸から渡ってきていた。
犬の毛皮も、乗員の人数分積んである。
これがあれば、波をかぶっても体温が保てる。
ハトを入れた鳥かごもある。
「方向を見失い、いよいよというときに空に向けて放ち、漕ぎ出す方向を決める」と、タケ兄はいう。
……… 著者の安達さんは、様々な資料から、この物語の双胴舟の積載量についても考察してます。
丸太をくり抜いた1艘の丸木舟は、板式底幅57cm、高さ29cm、長さ7m。
これを、2艘横に並べて連結。
その上に竹材を広げて甲板にして、竹で作った小さな小屋を載せている。
周りを竹材で補強し、多少浮力を補っている。
乗り込むのは、体重70㎏の大人の男性が13人で900㎏。
13人分の真水・食料・炭を積む。
それに帆と帆柱、石製の錨などを合わせると400㎏。
となると。
この双胴舟には 14石=180kg×14=1720kg が積載可能…とはじき出してます。
トキ爺 - 食事担当
真ん中の小屋には、真水と、玄米やイモやマメが入った大きな瓶が縛り付けてある。
炭もある。
火鉢が固定されていて、それにピッタリとはまる土鍋もあり、煮炊きができる。
ここで食事の用意をするのがトキ爺。
朝飯をつくったら、すぐに昼飯の準備。
昼がおわると、もう夕飯にとりかかる。
皆の疲れ具合をみて、トキ爺は「今日はコメ粥だぞ!」と声をだす。
航海は10日余り。
大陸が見えてきた。
大陸が見えたが、不用意に近づくと、息慎族から襲撃される。
舟は陸沿いに、安全なフヨの入り江に向かう。
山の形を確かめ ― 山当て ― ながら、位置を測る。
いつもの掛け声があって、櫂を握った舟子の掛け声が重なった。
「えーんや!」
「おーい!」
トキ爺は、水瓶から大きな柄杓すくって、「水はどうだ」と勧めて回る。
舟は、フヨの入り江に到着した。
……… ここは現在のウラジオストクの南のアムール湾あたり。
交易が盛んな大集落があったと、この物語では描かれてます。
このあとのトキ爺は描かれてません。
が、すでに帰りの水と食料と炭を調達をしていたのかもしれない…と、私は想像してます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ この物語を目にしたきっかけ ■
■ 主人公ナオトの旅の風景に触れてみてください ■
ヒダカの舟乗りたち
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| トップページ | この書店のこと | 購入 | お問い合わせ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━